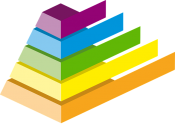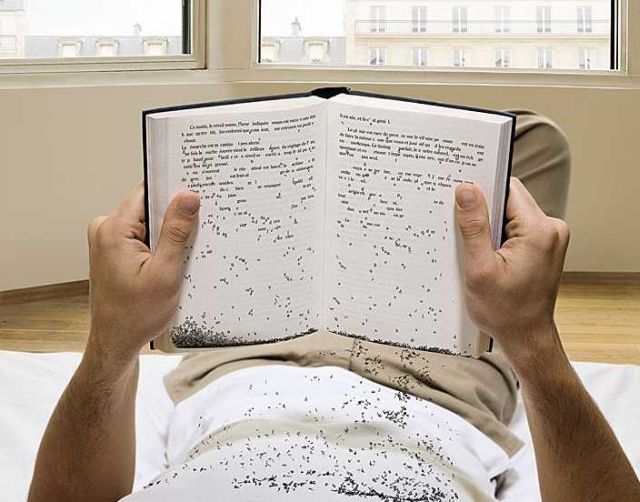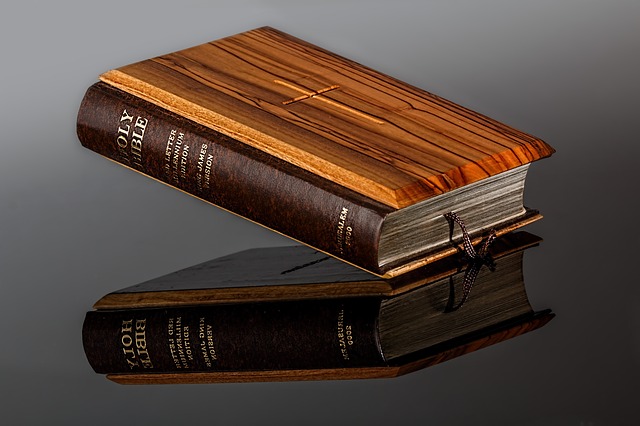社会人の勉強=実践して成果を出すこと。効果的なインプットとアウトプットの秘訣

Sei書著者・Seikiです。
読書についてあれこれ記事を書いているので
「勉強熱心ですねぇ」
「ストイックですね」
と言われることが多いんですが、
実際はそんなことなくて、単にインドアでダラダラ過ごしているだけです(笑)
それでも、人並み以上には本を読んできた中で
「身になる読書」と
「読んでおしまい」の読書の違いはよーく分かってます。
今日は前者の、身になる読書について解説し、
あなたのスキルアップのヒントを伝えるね。
Contents
インプットのバランス:いい加減に勉強するくらいでちょうどいい
私が個人的に思うことですが、
学校の勉強や資格試験などのペーパーテストを除けば、
いい加減に勉強するくらいでちょうどいいんですよ。
というのは、仕事であれ、趣味であれ、
ペーパーテストみたいに細かいところまで正確に答える必要なんかないし、
そもそもリアルの世の中に「正解」なんてものはないわけで(「意見の相違」があるのみ)、
ペーパーテストみたいな「インプット100%」という勉強の仕方をしたところで、
無意味!
私なりのインプット法:マックス60分
人間の注意力(集中力)というものは、限られた資源です。
連続で30分、累計なら1日に4時間くらいが限度だそうな。
つまり、学校も仕事も、人間のそういう理に適った運営の仕方をされていないから
生産性が低いってことだけど、
まぁそれは置いておきましょう。
私が何かを勉強するときには、
60分経ったらもう止めるようにしてます。
それ以上取り組んでも集中力が切れているし(学校の授業、特に大学の講義を思い出すと良いでしょう)、
有限で貴重な注意力という資源をアウトプットの方に回したいし、
締め切りを明確にしておくことで勉強もメリハリがつくんですよね。
ノッてるときにあえて止めることで「もっとやりたい!」と自分で自分を焦らしてあげる効果もあったりするし。
ちなみに速読すれば60分で2〜3冊読むくらいは余裕ですよん。
インプット>プロセス>アウトプット>成果
- インプット:本を読んだりセミナーに通ったりする
- プロセス:自分の頭で考えたり整理したり発想したりする
- アウトプット:実際にやってみる
- 成果:行動の結果
この一連の流れと、そのバランスこそが社会人の勉強、
リアルな学習です。
ペーパーテストのような勉強の方が「不自然」なのですよ。
行動してなんぼなのがリアルワールドなのだから。
アウトプットの秘訣:さっさとやる!
本を読んだりセミナーに通ったりしても、
「勉強しておしまい」になって行動に移せない人っていますよね。
まぁ、かつての私のことだけどさ。
ペーパーテストを除くあらゆる勉強は
行動まで結びつかなきゃ無意味なわけですが、
では行動に結びつけるには?
行動の原則:一個ずつ、1歩ずつ
人間は身1つですし、
時間も1日に24時間しか与えられていません。
なにが言いたいかって、
アレコレやろうとしても無理!ってことで、
一個ずつ、それもできるとこから一歩ずつ進んでいくしかないんですよ。
たとえば筋トレでも、いきなり
「片手懸垂できるようになりたい!」って不健康なデヴが言ってきたとしても
「いや、まずは普通の懸垂ができるようになってからね?話はそれからよ」
って感じだし、
できることから積み上げていくしかないんです。
行動力が弱い人=頭の中でハードルをあげて重くしてしまう人
つまり中々行動できない人ってのは
- あれこれやろうとしてしまう>結果としてどれも行動できない
- 完璧主義になって自分で勝手にハードルをあげてしまう>だから腰が重くなって行動に移せない
って感じです。
裏を返せば行動に移すヒントは、自転車の最初の一漕ぎのように
- 第一歩を徹底的に軽くする:5分以内に行動できるレベルまで細分化する
- あれこれやろうなんて思わず、一個か、せいぜい2個、確実に実践する:やっていくうちに他の行動に波及してくる
って話。
私は
筋トレもヨガも瞑想も気功も、簡単な一歩から初めて今に至るからね。
まずは腕立てをできるところまでやることから始めて、いまでは自重トレーニングのマスターとなったし、
立禅を5分程度やることからスタートして、いまでは気功にハマってるからね。
最初の一歩がどんどん勢いづいた結果です。
まとめ:成果を出せ!それが成長であり成績である
ペーパーテスト以外の勉強は成果こそが、試験における点数です。
100点満点で終わることのない、青天井に無限に点数を伸ばせるテストですね。
何かを極めることに終わりはないってことよ。
仕事、料理、武道、芸術、なんでもそうでしょ?
だからこそ
いいかげんに勉強し、さっさと行動して、結果を出してしまう
のが社会人の、リアルワールドの勉強法なのです。